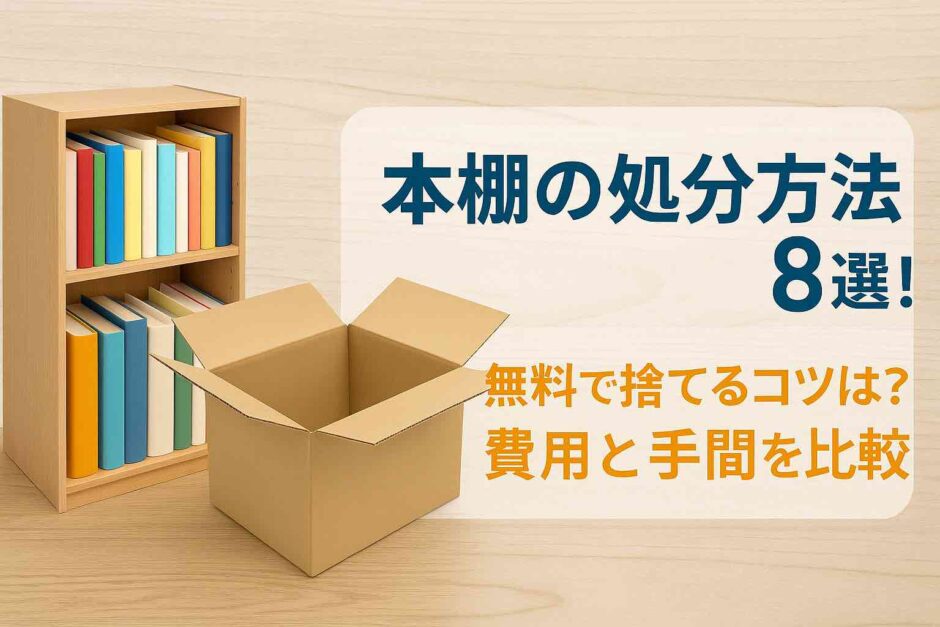引っ越しや模様替え、断捨離などをきっかけに、これまで活躍してくれた本棚が不要になることも少なくありません。いざ処分しようとすると、「どうやって捨てればいいのだろう?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問が次々と湧いてくるのではないでしょうか。
本棚はサイズが大きく、重量もあるため、処分には手間や費用がかかるケースがほとんどです。しかし、その方法は一つではありません。自治体のサービスを利用する方法から、売却してお得に手放す方法まで、さまざまな選択肢があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
この記事では、本棚を処分する方法8選と、本棚の解体する方法と注意点を解説します。また、よくある質問も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
本棚を処分する方法8選
不要になった本棚を処分するには、様々な方法があります。ここでは、代表的な8つの方法と、それぞれにかかる費用の相場をご紹介します。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
| 処分方法 | 費用の目安 | 手間 | おすすめな人 |
| 自治体の粗大ゴミ | 500円~2,000円程度 | △ | 費用を抑えたい人 |
| 自治体の処理施設 | 0円~1,500円程度 | △ | 車での運搬が可能な人 |
| 自治体の一般ゴミ | 0円(指定袋のみ) | × | 費用をかけたくない人 |
| リサイクルショップ | 0円(収益あり) | △ | 手間なく現金化したい人 |
| フリマアプリやネットオークション | 0円(収益あり) | × | 少しでも高く売りたい人 |
| 家具店の引き取りサービス | 3,000円~4,400円程度 | ○ | 買い替えを検討している人 |
| 不用品回収業者 | 数千円~ | ○ | 他の不用品とまとめて処分したい人 |
| 友人や知人に譲渡 | 0円 | △ | 必要とする人に使ってほしい人 |
※手間:○=手間ゼロ・△=やや手間がかかる・×=手間がかかる
方法1:自治体の粗大ゴミに出す
最も一般的なのが、自治体の粗大ゴミ収集を利用する方法です。手続きは自治体によって多少異なりますが、一般的には事前の申し込みと手数料の支払いが必要です。
費用は本棚のサイズによって変動し、おおよそ500円から2,000円程度が相場です。この方法の最大の利点は、他の方法に比べて費用を安く抑えられることと、自治体が運営しているため不法投棄などの心配がなく安心して依頼できる点です。
粗大ゴミを利用する手順
- 自治体の粗大ゴミ受付センターに連絡
電話またはインターネットで申し込みます。その際に、本棚のサイズ(高さ・幅・奥行き)を伝えると、手数料を案内されます。 - 手数料納付券(処理券・シール)を購入
案内された金額分の手数料納付券を、地域のコンビニエンスストアやスーパー、郵便局などで購入します。 - 手数料納付券を貼りつけ
購入した券に氏名や受付番号などを記入し、本棚の見やすい場所に貼りつけます。 - 指定の日時に搬出
収集日の朝、指定された場所(玄関先、敷地の入り口、ゴミ集積所など)に本棚を運び出します。
本棚は重く大きいため、一人で運び出すのが困難な場合があります。運び出しが可能かどうか検討してから依頼しましょう。
 カタニャン
カタニャン
| メリット | デメリット |
| 処分費用が安い | 申し込みや搬出に手間がかかる |
| 自治体運営で安心 | 日時の指定が難しい |
方法2:自治体の処理施設に直接持ち込む
お住まいの自治体のゴミ処理施設(クリーンセンターなど)へ直接持ち込む方法もあります。自分で運搬する手間はかかりますが、戸別収集よりも費用を抑えられる可能性があります。
費用は重量制で計算されることが多く、「10kgあたり〇〇円」といった料金設定が一般的です。自治体によっては一定の重量まで無料の場合もあり、相場としては無料から1,500円程度です。
 カタニャン
カタニャン
ただし、この方法を利用する場合は、本棚を運べる車が必要です。自家用車がない場合はレンタカー代が別途かかり、かえって高くつくこともあります。
| メリット | デメリット |
| 費用が非常に安い、または無料 | 運搬用の車が必須 |
| 自分の都合で即日処分できる | 積み込み・荷下ろしを自分で行う必要がある |
| 予約なしで持ち込める場合がある | 施設の場所が遠い場合がある |
方法3:自治体の一般ゴミ(可燃ゴミ・不燃ゴミ)に出す
本棚を工具を使って解体し、自治体が指定するサイズ以下にすれば、一般ゴミ(可燃ゴミ・不燃ゴミ)として無料で処分が可能です。多くの自治体では、「一辺の長さが30cm(または50cm)以内」といった基準が設けられています。
この方法であれば、処分の手数料はかかりません。また、可燃ゴミや不燃ゴミは週に1〜2回収集があるため、自分のタイミングで捨てやすい点も魅力です。
しかし、本棚の解体は想像以上に大変な作業です。特に木材が厚いものや、接着剤で強力に固定されているものは、分解するだけでも多大な労力と時間を要します。
のこぎりやハンマー、軍手といった工具を揃える必要があり、作業には怪我のリスクも伴うため、この方法を選ぶ際は慎重に検討しましょう。
| メリット | デメリット |
| 処分費用が無料 | 解体に多大な労力と時間が必要 |
| 収集日が頻繁にある | 工具の準備が必要 |
| 自分のタイミングで捨てられる | 怪我や騒音のリスクがある |
方法4:リサイクルショップで売却する
本棚の状態がよく、まだ十分に使えるものであれば、リサイクルショップに買い取ってもらう方法があります。有名家具メーカーのものやデザイン性の高いものであれば、思わぬ高値がつく可能性もあります。
売却できれば処分費用はかからず、逆に収入になります。買取価格は数百円から数千円が一般的ですが、ブランドや状態によってはそれ以上になることもあります。また、出張買取サービスを利用すれば、査定から運び出しまで全てスタッフに任せられるため、手間もかかりません。
しかし、傷や汚れがひどいもの、デザインが古いものなどは買取価格がつかない、あるいは引き取り自体を断られるケースも少なくありません。
高く売るためには、査定前に綺麗に掃除をしておくこと、可動式の棚板や説明書などの付属品を揃えておくことが重要です。
 カタニャン
カタニャン
| メリット | デメリット |
| 処分費用が無料になり収入になる | 必ず売れるとは限らない |
| 手間が少ない(出張買取の場合) | 買取価格が安い傾向にある |
| 環境に貢献できる | 持ち込みの場合は運搬が大変 |
方法5:フリマアプリやネットオークションで売却する
メルカリやヤフオク!などのフリマアプリやネットオークションを利用して、個人間で売買する方法です。リサイクルショップよりも高値で売れる可能性がありますが、出品から発送まで全て自分で行う必要があります。
売却できれば収入になりますが、販売価格の10%前後の販売手数料と、送料がかかることを忘れてはいけません。また、商品の写真撮影、説明文の作成、購入者とのやり取り、発送という一連の作業を全て自分で行う必要があります。
手順
- 出品
本棚の写真を撮り、サイズ、状態、ブランドなどの情報を詳しく記載して出品します。 - 価格設定:
送料や手数料を考慮して、販売価格を設定します。「梱包・発送たのメル便」のような大型家具専用の配送サービスを利用すると、手間は省けますが送料は高くなります。 - 購入者とのやり取り
商品に関する質問に答えたり、値下げ交渉に応じたりします。 - 梱包・発送
商品が売れたら、傷がつかないように丁寧に梱包し、配送手続きを行います。
特に大型家具の梱包は非常に手間がかかり、送料も数千円から1万円以上かかることが珍しくないため、手間や送料を考慮した価格設定が必要です。
すぐに買い手が見つかるとは限らず、個人間取引ならではのトラブルのリスクもあります。時間や手間をかけられる人向けの方法です。
| メリット | デメリット |
| 高値で売れる可能性がある | 出品から発送まで全て自分でやる必要がある |
| 自分で価格を設定できる | 送料が高額になりやすい |
| ニッチな商品でも売れる可能性がある | すぐに売れるとは限らない |
方法6:家具店の引き取りサービスを利用する
新しい本棚の購入を検討している場合、購入店の引き取りサービスを利用できることがあります。ニトリやIKEA、無印良品などの大手家具店でサービスを実施している場合が多く、費用は3,000円から4,400円程度が相場です。
このサービスの最大の利点は、新しい本棚の搬入と古い本棚の搬出を一度に済ませられる効率の良さです。配送スタッフが部屋の中から運び出してくれるため、重い本棚を自分で運ぶ手間が一切かかりません。
ただし、新しい家具の購入が前提で、「購入した家具と同等品・同数量」といった条件が設けられていることがほとんどです。引き取りだけを依頼することはできず、サービス自体も有料です。
利用を検討する際は、購入予定の店舗のウェブサイトなどで、サービスの詳細な条件(料金、対象品目、引き取り場所など)を必ず事前に確認してください。
手順
- サービスの有無と条件を確認
家具を購入する店舗で、引き取りサービスを行っているか、またその利用条件を確認します。 - 家具の購入と同時に申し込む
店舗のレジやオンラインストアの注文画面で、新しい家具の購入手続きと同時に引き取りサービスを申し込みます。 - 引き渡し
配送日当日、スタッフに古い本棚を引き渡します。事前に中身を空にしておく必要があります。
| メリット | デメリット |
| 買い替えと処分が同時にできる | 新しい家具の購入が前提 |
| 運び出しの手間がない | 引き取りのみは不可 |
| 信頼できる業者に任せられる | 費用がかかる |
方法7:不用品回収業者に依頼する
手間をかけずに、迅速に本棚を処分したい場合に最も適しているのが、不用品回収業者に依頼する方法です。電話やウェブサイトから申し込むだけで、希望の日時に自宅まで回収に来てくれます。
費用は業者や本棚のサイズによって大きく異なりますが、3,000円から10,000円程度が相場です。ただし、他の不用品とまとめて回収してもらうと、一点あたりの費用は割安になる場合もあります。
部屋からの運び出し、運搬まで全ての作業を業者が行ってくれるため、最も楽な方法といえます。ただし、他の方法に比べて費用が高額になる傾向があります。
業者の中には無許可で営業し、高額請求をしたり不法投棄をしたりする悪質な業者も存在するため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
不用品回収業者の選び方
- 「一般廃棄物収集運搬業」の許可を確認する
家庭ゴミを回収するには、市区町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。ウェブサイトの会社概要などで許可の有無を必ず確認しましょう。「産業廃棄物」や「古物商」の許可だけでは家庭ゴミの回収はできません。 - 見積もりを書面で提示してくれるか
必ず作業前に、内訳が明記された書面の見積もりを依頼しましょう。口頭での見積もりだけで、後から高額な追加料金を請求するトラブルを避けるためです。 - 会社の所在地や連絡先が明記されているか
ウェブサイトに会社の住所、電話番号がきちんと記載されているかを確認します。所在地が不明確な業者は信頼性に欠ける可能性があります。
1社だけで決めず、2〜3社から見積もりを取って料金やサービス内容を比較検討することが、不当に高い料金を支払うリスクを減らす上で重要です。
| メリット | デメリット |
| 手間が一切かからない | 費用が比較的高額 |
| 日時を自由に指定できる | 悪質な業者が存在する |
| 他の不用品もまとめて処分可能 | 単品だと割高になることがある |
方法8:友人や知人に譲渡する
もしあなたの周りに本棚を必要としている友人や知人がいれば譲るという選択肢もあります。大切に使ってきた本棚を、費用をかけずに処分でき、相手にも喜んでもらえる、双方にとってメリットのある方法です。
しかし、当然ながら譲る相手が見つからなければ成立しません。また、運搬をどうするかという問題も発生します。相手が車で取りに来てくれるのが理想ですが、そうでない場合は自分で運んだり、配送業者を手配したりする必要があり、その際の費用負担についても事前に話し合っておく必要があります。
 カタニャン
カタニャン
| メリット | デメリット |
| 処分費用がかからない | 譲る相手を見つける必要がある |
| 大切な家具を再利用してもらえる | 運搬方法を相談する必要がある |
| 手間が比較的少ない | トラブルになる可能性がある |
本棚の解体方法と注意点
処分費用を抑えるために本棚の解体を検討している方向けに、具体的な手順と安全に行うための注意点を解説します。作業には危険が伴うため、準備を万全にしてから取り掛かりましょう。
解体作業を始める前の準備
まず、解体作業を安全に行うための準備が必要です。
作業スペースとして、家具や障害物のない広い場所を確保し、床が傷つかないようにブルーシートや古い毛布、段ボールなどを敷きましょう。
作業中の怪我を防ぐため、滑り止めつきの軍手や、目を守るための保護メガネを必ず着用してください。
必要な工具として、ネジを外すためのドライバー(電動ドライバーがあると便利)、板を分解するためのバールやハンマー、大きな板を切断するためののこぎりを用意します。
 カタニャン
カタニャン
本棚を解体する手順
準備が整ったら、以下の手順で解体作業を進めます。
- ネジや金具を外す
まずはドライバーを使い、背板を固定しているネジや、棚を連結している金具などを全て取り外します。ネジ穴が潰れてしまっている場合は、ペンチで頭を掴んで回すと外れることがあります。 - パーツを分解する
ネジを全て外したら、側板、天板、底板、棚板などの各パーツに分解します。接着剤で固定されていて手で外れない場合は、ゴムハンマーで軽く叩いたり、板の隙間にバールを差し込んで慎重にこじ開けたりします。力を入れすぎると板が割れて破片が飛び散ることがあるので注意してください。 - 大きな板を切断する
分解した板が、自治体の指定するゴミのサイズ(一辺30cmなど)をまだ超えている場合は、のこぎりで切断します。板をしっかりと固定し、焦らずゆっくりと切断作業を進めましょう。
解体が終わったら、木材(可燃ゴミ)、ネジや金具(不燃ゴミ・金属ゴミ)、ガラス扉など、素材ごとに分別します。この分別を怠ると、ゴミとして収集してもらえない可能性があるので注意が必要です。
解体時の注意点
本棚の解体で最も注意すべきなのは、怪我のリスクです。古くなった木材はもろく、ささくれが刺さりやすい状態になっています。また、錆びた釘やネジで手を切ると、破傷風の原因になる可能性もあります。
工具の取り扱いにも十分な注意が必要で、特に電動工具やのこぎりを使う際は、一瞬の不注意が大きな事故につながりかねません。また、時間と労力が予想以上にかかることも覚悟しておきましょう。頑丈な本棚の場合、数時間かけても解体できないこともあります。
 カタニャン
カタニャン
本棚の処分でよくある質問
本棚の処分に関して、多くの方が抱える疑問点や不安をQ&A形式でまとめました。
傷や汚れがひどい本棚でも売れますか?
難しい可能性が高いです。リサイクルショップでは、目立つ傷や汚れ、破損、カビ、シールの貼りつけなどがある場合、買取を断られるか、引き取り自体を拒否されるケースがほとんどです。 フリマアプリでも、状態が悪いものは買い手がつきにくく、クレームの原因にもなります。
状態が悪い本棚は、売却ではなく「自治体の粗大ゴミ」や「不用品回収業者」での処分を検討するのが現実的です。
本棚を無料で処分する方法はありますか?
はい、以下の方法であれば無料で処分できる可能性があります。
- 解体して一般ゴミに出す
最も費用がかかりませんが、工具の準備や解体の手間、時間がかかります。 - リサイクルショップで売却する
状態がよく、ブランド品であれば収入になる可能性があります。 - フリマアプリで売却する
高値で売れる可能性がありますが、梱包・発送の手間と高額な送料がかかります。 - 友人や知人に譲渡する
相手さえ見つかれば、お互いにとってよい方法です。
ただし、売却や譲渡は本棚の状態が比較的よい場合に限られます。
自分では運び出せないのですが、どうすればよいですか?
ご自身での運び出しが困難な場合は、専門のスタッフが室内から搬出してくれるサービスを利用しましょう。
- 不用品回収業者に依頼する
費用はかかりますが、最も手間がなくスピーディーです。 - リサイクルショップの出張買取
売却が成立すれば、運び出しまで任せられます。 - 家具店の引き取りサービス
新しい家具に買い替える場合のみ利用できます。
自治体の粗大ゴミは、原則として自宅内からの運び出しは行っていないため、玄関先や指定場所まで自分で運ぶ必要があります。
本棚は解体しないと捨てられませんか?
いいえ、必ずしも解体が必要なわけではありません。「粗大ゴミ」「処理施設への持ち込み」「不用品回収業者」などは、基本的に解体は不要で、そのままの状態で引き取ってもらえます。
解体が必要になるのは、処分費用を節約するために一般ゴミとして捨てたい場合のみです。
自分に合った方法で本棚を賢く処分しよう
ここまで、本棚を処分するための8つの方法と、解体の手順や注意点について詳しく解説してきました。最適な処分方法は、状況や何を優先するかによって大きく異なります。
費用を何よりも安く抑えたいのであれば、手間と時間はかかりますが、自力で解体して一般ゴミとして出すか、運搬手段を確保して自治体の処理施設へ直接持ち込むのが最善の選択肢となるでしょう。
一方で、手間をかけずに素早く処分したいと考えるなら、費用はかかりますが不用品回収業者に依頼するのが最も簡単で確実な方法です。運び出しから全てを任せられるため、時間がない方や体力に自信がない方には最適です。
もし本棚がまだ綺麗で十分に使える状態ならば、リサイクルショップやフリマアプリで売却することでお得に処分できる可能性があります。これは処分費用をなくすだけでなく、収入にも繋がる賢い選択です。また、新しい本棚への買い替えを計画している場合には、購入店の引き取りサービスを利用することで、新しい家具の搬入と古い家具の搬出を一度に済ませることができ、非常に効率的です。
それぞれの方法のメリットとデメリットをよく比較検討し、ご自身の本棚の状態、予算、そしてかけられる時間や労力に照らし合わせて、最も納得のいく方法を選びましょう。