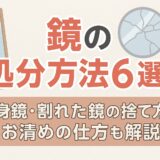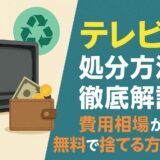通販や引越しの後など、気づけば家にたまってしまう段ボール。置き場所を取るし、早く片付けたいけれど「どうやって捨てるのが一番いいんだろう?」と迷ったことはありませんか?
実は段ボールの処分方法にはいくつも選択肢があり、状況に合わせて選ぶことで手間も費用もぐっと変わってきます。
この記事では、段ボールを処分する7つの方法と、捨てる前に必ずするべき3つの準備について解説します。また、よくある質問についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
段ボールの処分方法7選
段ボールの処分は、費用をかけずに自分で処理する方法から、専門業者に任せる方法まで、選択肢は多岐にわたります。処分したい段ボールの量やかけられる手間などに合わせて最適な方法を選んでください。
| 捨て方 | 費用 | 手間 | こんな人におすすめ |
| 自治体の資源ごみとして出す | 0円 | △ | 少量の段ボールを手軽に無料で処分したい人 |
| 自治体のゴミ処理施設へ持ち込む | 0〜数百円(重量により数十円程度) | △ | 車を持っていて、大量の段ボールを一度に安く処分したい人 |
| 地域の集団回収・古紙回収 | 0円 | △ | 地域貢献もしながら処分したい人 |
| スーパーなどの回収ボックス | 0円 | ○ | 買い物ついでにすぐ処分したい人 |
| 古紙回収業者に依頼・持ち込み | 0円〜(持込無料/回収は有料の場合あり) | △ | 大量の段ボールをまとめて処分したい人、ポイントでお得に処分したい人 |
| 不用品回収業者に依頼 | 数千円〜数万円 | ○ | 手間をかけずに他の不用品とまとめて処分したい人 |
| 引越し業者に引き取ってもらう | 0円(プランにより有料) | ○ | 引越し時にまとめて処分したい人 |
※手間:○=手間ゼロ・△=やや手間がかかる・×=手間がかかる
捨て方1:自治体の資源ごみとして出す
最も身近で、多くの人が利用しているのが、お住まいの自治体の資源ごみとして出す方法です。決められた曜日の朝、指定された集積所に出しておくだけで回収してもらえるため、非常に手軽です。
この方法の最大のメリットは、何と言っても無料で処分できること。特別な手続きも必要なく、普段のゴミ出しと同じ感覚で捨てられるのは大きな魅力です。数枚程度の少ない量の段ボールを処分したい場合には、最も合理的で経済的な選択肢と言えるでしょう。
資源ごみの回収は、多くの自治体で月に1〜2回程度と頻度が少ないため、すぐに処分したいと思っても次の回収日まで待たなければなりません。また、一度に大量の段ボールが出た場合、集積所まで自分で何度も往復して運ぶのはかなりの重労働になります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で処分できる | 回収頻度が月1〜2回と少ない |
| 特別な手続きが不要 | すぐに処分できない場合がある |
| 普段のゴミ出しと同じ感覚で手軽 | 大量の段ボールは運搬が大変 |
| 少量処分には最も合理的で経済的 | 集積所まで何度も往復する必要がある |
捨て方2:自治体のゴミ処理施設へ持ち込む
引越しや大掃除などで一度に大量の段ボールが出た場合、自治体のゴミ処理施設に持ち込むという方法もあります。この方法の最大のメリットは、自分の都合の良いタイミングで、大量の段ボールを一度に処分できる点です。自治体の回収日を待つ必要がなく、「今すぐこの段ボールの山をなくしたい」というニーズに応えてくれます。
また、処理手数料は無料または非常に安価(例:10kgあたり数十円など)で済むことがほとんどで、経済的な負担が少ないのも魅力です。ただし、施設まで自分で運搬するための車が必須となります。
 カタニャン
カタニャン
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 自分のタイミングで大量処分できる | 車が必須になる |
| 処理費用が安価または無料 | 施設が平日日中のみのことが多い |
| 一度にまとめて処理できる | 運搬の手間がかかる |
| 急ぎの処分に対応できる | 事前にルール確認が必要 |
捨て方3:地域の集団回収・古紙回収を利用する
自治会の子供会や町内会、マンションの管理組合などが主体となって行っている「集団回収」や「古紙回収」を利用する方法もあります。これも無料で段ボールを処分でき、なおかつ回収によって得られた収益が地域の活動資金になるなど、間接的に地域貢献ができるというメリットがあります。
回収場所が自宅の近くだったり、マンションのエントランスだったりすることが多く、資源ごみの集積所よりも近い場所で処分できる可能性もあります。
実施されるタイミングは数ヶ月に一度など、自治体の資源ごみ回収よりもさらに頻度が低いケースがほとんどです。そのため、実施日を逃してしまうと、次の機会まで長期間段ボールを保管しなくてはなりません。
 カタニャン
カタニャン
タイミングさえ合えば、無料で手軽に利用でき、地域のためにもなる一石二鳥の方法です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で処分できる | 実施頻度が数ヶ月に1回程度と少ない |
| 地域活動の資金に貢献できる | タイミングを逃すと保管が必要 |
| 自宅近くで回収されることが多い | 情報をこまめに確認する必要がある |
| 手軽かつ地域貢献につながる | 自由度が低い |
捨て方4:スーパーなどの回収ボックスに持ち込む
近所のスーパーマーケットやドラッグストア、ホームセンターの店先に、段ボールや古紙を回収するためのボックスが設置されている場合があります。これも無料で段ボールを処分できる、非常に便利な方法です。
この方法の魅力は、なんといってもその手軽さです。店舗の営業時間内であれば、自分の好きなタイミングでいつでも持ち込んで処分することができます。「次の資源ごみの日まで待てない」「今すぐこの段ボールを片付けたい」という時に非常に役立ちます。
店舗によっては回収できる段ボールのサイズや量に制限がある場合や、その店舗で購入した商品の段ボールのみを対象としているケースもあります。持ち込む前には、回収ボックスの案内表示などを一度確認しておくと安心です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で処分できる | 店舗によって制限がある場合がある |
| 営業時間内ならいつでも利用可 | 購入商品の段ボールのみ対象のこともある |
| 買い物ついでに処分できる | 一度に持ち込める量に限りがある |
| 即日処分できて便利 | 事前確認が必要 |
捨て方5:古紙回収業者に依頼・持ち込む
古紙の回収を専門に行う古紙回収業者を利用する方法があります。これには大きく分けて「自分で持ち込む」ケースと「自宅まで回収に来てもらう」ケースの2つがあります。
自分で業者(リサイクルステーションや古紙回収センターなど)の拠点まで持ち込む場合は、無料で引き取ってもらえることがほとんどです。中には24時間無人で受け付けている拠点もあり、時間を一切気にせず処分できるのが大きなメリットです。
 カタニャン
カタニャン
一方、自宅まで回収に来てもらう場合は、基本的に有料のサービスとなります。ただし、段ボールの量が非常に多い場合(数十kg以上など)や、他の古紙と合わせて大量に処分する場合には、無料で回収、あるいは買い取ってくれるケースもあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で引き取ってもらえることが多い | 自宅回収は有料になる場合が多い |
| ポイント付与や商品券交換など特典あり | 大量でないと無料回収対象にならない |
| 24時間受付の無人拠点もある | 業者によって条件が異なる |
| 大量処分に対応可能 | 持ち込み先まで運搬が必要 |
捨て方6:不用品回収業者に依頼する
「とにかく手間をかけたくない」「引越しや大掃除で出た大量の段ボールを、他の不用品と一緒に今すぐ処分したい」。そんなニーズに応えてくれるのが、不用品回収業者への依頼です。
このサービスの最大のメリットは、「手間のかからなさ」です。電話やウェブサイトから申し込むだけで、希望の日時に自宅まで回収に来てくれます。段ボールを玄関先に出しておくだけでよく、場合によっては部屋の中から運び出してもらうことも可能です。
ただし、便利なサービスである分、費用が高めです。料金体系は業者によって様々ですが、「トラック載せ放題プラン」などで数万円単位の費用が発生することが一般的です。段ボールだけの回収だと割高に感じられるかもしれませんが、他にも処分したい家具や家電がある場合には、結果的にコストパフォーマンスが高くなることもあります。
業者を選ぶ際には、必ず「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得ているかを確認しましょう。無許可の業者に依頼すると、不法投棄や高額請求などのトラブルに巻き込まれる危険性があります。
 カタニャン
カタニャン
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 手間をかけずに処分できる | 費用が高額(数千円〜数万円) |
| 他の不用品とまとめて処分可能 | 段ボールだけだと割高に感じる |
| 玄関先や室内から回収してもらえる | 業者選びを誤るとトラブルの可能性 |
| 希望日時に回収してくれる | 許可業者か確認が必要 |
捨て方7:引越し業者に引き取ってもらう
引越し業者に無料で引き取ってもらう方法もあります。引越しをする際に限定される方法ですが、引越し後の荷解きが終わるタイミングを見計らって回収に来てくれるため、自分で大量の段ボールを処分する手間がかかりません。
ただし、このサービスは全ての引越しプランに含まれているわけではなく、有料のオプションであったり、対応エリアが限定されていたりする場合があります。
また、引き取ってもらえるのは、その引越し業者が提供した段ボールのみで、自分で用意した段ボールは対象外となるのが一般的です。引越しの見積もりを取る段階で、段ボールの引き取りサービスの有無、料金、条件などを必ず確認しておくようにしましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で回収してもらえる場合がある | プランや業者によって有料の場合もある |
| 引越し後すぐに処分できる | 提供された段ボールのみ対象が多い |
| 自分で運ぶ手間が不要 | サービスがエリア限定の場合がある |
| 荷解きのタイミングに合わせて回収 | 見積もり段階での確認が必要 |
段ボールを処分する前に必ずすべき3つの準備
どの処分方法を選ぶにしても、段ボールを捨てる前にはいくつかの大切な準備が必要です。これを怠ると、回収を拒否されたり、思わぬトラブルの原因になったりすることもあります。スムーズな回収のために、以下の3つのポイントを必ず実践しましょう。
1.伝票や宛名を剥がして個人情報を守る
段ボールを処分する上で最も重要な準備が、伝票や宛名を剥がすことです。
通販などで届いた段ボールには、あなたの氏名、住所、電話番号といった個人情報が記載された伝票や宛名ラベルが貼られています。これをそのままにして捨ててしまうと、第三者に個人情報を悪用されるリスクがあり、非常に危険です。
どうしても剥がれない場合は、個人情報保護スタンプや黒い油性マーカーで文字情報が読めないように塗りつぶしましょう。
2.テープや金具などを取り除く
段ボールをまとめる前に、ガムテープやビニールテープ、梱包用のPPバンド、ホッチキスの芯など、段ボール以外のものは全て取り除くことが重要です。
段ボールは製紙工場で水に溶かされ、再び紙の原料として生まれ変わります。その過程で、紙以外の異物が混ざっていると、機械の故障の原因になったり、再生紙の品質を低下させたりしてしまいます。
面倒に感じるかもしれませんが、質の高いリサイクルを実現し、地球の資源を未来につなげていくための大切な作業です。
3.潰してコンパクトにし、紙紐で十字に縛る
段ボールは、箱のままではなく、必ず平らに潰してからまとめましょう。かさを減らすことで、運搬や保管がしやすくなり、回収する人の負担も軽減されます。
潰した段ボールは、大きさをある程度揃えて重ね、荷崩れしないように紐で縛ります。この時、ビニール紐やガムテープでまとめるのは避けましょう。これらもリサイクルの際の異物となってしまうためです。
推奨されているのは「紙紐」です。紙紐であれば、段ボールと一緒にリサイクル工程に回せるため、回収後に紐を解く手間が省けます。
縛り方は、段ボール束の縦と横に紐をかける「十字縛り」が基本です。持ち上げた時にバラバラにならないよう、きつめに縛るのがコツです。
段ボールの処分に関するよくある質問
ここでは、段ボールの処分に関して多くの人が疑問に思う点を、Q&A形式で解説します。
雨の日に資源ごみで出していいですか?
結論から言うと、雨の日に段ボールを出すのは避けるのが賢明です。段ボールは紙でできているため、水に濡れると強度が著しく低下し、リサイクル原料としての品質も落ちてしまいます。濡れた段ボールはカビの発生原因にもなり、衛生的にも良くありません。
自治体によっては、雨天時には古紙類を出さないようにと明確に指示している場合もあります。もし回収日の朝に雨が降っていたら、無理に出さずに次の回収日まで自宅で保管するのが最も確実な対応です。
どうしてもその日にしか出せない事情がある場合は、ビニールシートを被せるなど、極力濡れないような配慮をすることが望ましいです。
汚れたり濡れたりした段ボールはどうすればいいですか?
汚れや濡れの程度によって対応が変わります。例えば、表面に少し泥がはねた、一時的に濡れたけれど完全に乾いていて強度も問題ない、といった軽微なものであれば、多くの場合リサイクル可能です。
しかし、油が染み込んでいたり、食品の汚れや臭いがひどかったり、濡れてふやけてしまったりしているものはリサイクルには適しません。このような段ボールは、残念ながら資源ごみではなく「燃えるごみ」として処分する必要があります。
捨てる前に段ボールの状態をよく確認し、リサイクルできるものとできないものを正しく見極めることが大切です。
会社やお店から出た段ボールも同じように捨てられますか?
いいえ、同じようには捨てられません。家庭から出るごみ(一般廃棄物)と、会社や店舗などの事業活動によって出たごみ(事業系廃棄物)は、法律で明確に区別されています。
会社やお店から出た段ボールは事業系廃棄物にあたるため、家庭ごみの集積所に出すことはできません。これは不法投棄と見なされる可能性があります。
事業系の段ボールは、その地域の自治体が許可した「事業系一般廃棄物収集運搬許可業者」と契約して回収してもらうか、自ら自治体の処理施設に持ち込むのが正規のルートです。事業者の責任として、ルールに則った適切な処分を徹底しましょう。
段ボールは状況に合わせて正しく賢く処分しよう
この記事では、7つの段ボール処分方法と、処分前に必ず行うべき大切な準備について詳しく解説しました。
日々の生活で出る少量の段ボールなら、コストのかからない「自治体の資源ごみ」や「スーパーの回収ボックス」が便利です。一方で、引越しや大掃除で出た大量の段ボールを、とにかく手間なくスピーディーに片付けたいなら、「不動品回収業者」が頼れる味方になるでしょう。
どの方法を選ぶにしても、個人情報を守り、リサイクルのために異物を取り除き、きちんとまとめてから処分するという基本は変わりません。
あなたのライフスタイルや段ボールの量に合った、最もストレスのない方法を選んで、溜まった段ボールを気持ちよく片付けましょう。